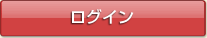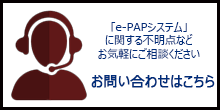役員退職金 ~社長の功績倍率が「3・0」と言われる本当の理由~
2020.11.06
役員退職金は、税務上の論点として不相当に高額な部分が損金不算入となるため、金額の大きさや算定式に注目が集まります。
法人税法34条では、原則損金算入を認めており、平成29年度税制改正の役員退職給与の見直しに伴い、いわゆる功績倍率法の定義が初めて明文化されました(以下、表参照)。
|
法人税基本通達9-2-27の2(業績連動給与に該当しない退職給与) いわゆる功績倍率法に基づいて支給する退職給与は、法第34条第5項((業績連動給与))に規定する業績連動給与に該当しないのであるから、同条第1項((役員給与の損金不算入))の規定の適用はないことに留意する。(平29年課法2-17「十二」により追加) (注) 本文の功績倍率法とは、役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう。 |
ただ、「功績倍率法」を用いる場合、類似法人の「最高功績倍率」または「平均功績倍率」のどちらを採用するか考えなくてはいけません。この点について東京地裁判決(2013年3月22日)では、優先すべきは「平均功績倍率法」としており、「最高功績倍率」を用いるときは、「同業類似法人の抽出基準が必ずしも十分でない場合」「その抽出件数が僅少であり、かつ、最高功績倍率を示す同業類似法人が極めて類似している場合に限る」としています。
功績倍率をベースとした役員退職金の算出は、
「最終役員報酬月額」 ×「役員在任期間」× 「功績倍率」= 役員退職金
となります。
過去の裁決事例や裁判例をみると、役員退職給与が不相当に高額か否かで争われているものが多く存在し、その争点の多くが「功績倍率」に関するものです。税理士業界ではよく「社長の功績倍率3・0が上限」と言われますが、その論拠は、東京高裁判決(昭和56年11月18日)が示した「社長3・0、専務2・4、常務2・2、平取締役1・8、監査役1・6」という数字が大きく影響しているようです。
しかし、この基準から外れた途端に否認されるかといえばそうではありません。「7・5」(東京高裁・昭和52年9月26日)でも認められています。一方で、「1・5」でも否認されているケースもあります。
とはいうものの、前述した東京高裁判決がそこまで実務的に影響している理由は、実は国税当局内部の事情も絡んでいるのです。
国税OB税理士によると、「計算方法で功績倍率が『3・0まで』というのは、税務当局の内部の取り扱いとして、納税者が『3・0』以上で計算してきたら、税務署(長)が判断するのではなく、国税局に上げて、合理的な金額を検討していくことになる」と言います。
つまり、国税局に上がると、担当は税務署であっても、実質的に国税局の判断に従うしかなく、税務署の担当者レベルの話し合いでなんとかすることができなくなるのです。
そのため、前出のOB税理士は「事案が国税局に上がらないように『3・0』を超えない範囲で計算することが重要で、その意味で実務上は『3・0』が大きな意味を思ってくる」と指摘します。
当局内部の問題と言ってしまえばそれだけのことですが、税務調査で争いたくない場合なら「3・0」にすることが安全といわれるのが、こうした意味も含んでいるようです。